
お盆も終わりのころ、公園や広場に櫓(やぐら)を組んで、その周りをぐるぐると回りながら、盆踊りをした経験はどなたにもあることでしょう。多くの人にとって、楽しい夏の思い出の一つですよね。
町内会が中心となって行われる、地域の盆踊りは今でも行われています。でも、なぜ盆踊りをするのか、その理由を知る方は少ないのではないでしょうか。
そこで、今回は、盆踊りの起こりや由来について調べてみました。
盆踊りの起源と由来
まずは盆踊りの始まり「起源」からご紹介していきます。
盆踊りの起源
盆踊りの起源は、平安時代中期までさかのぼります。
そのころ活躍していた僧侶、空也は、念仏を庶民に広める思案をしていました。瓢箪(ひょうたん)を手に持ってたたきながら、「節に合わせて念仏を唱える」と言う工夫をしました。この方法だと、手軽に念仏が唱えられると考えたのです。
また、その時、念仏に合わせて踊りを踊るようになり、これが念仏踊りとして広く世の中に知られるようになりました。
この念仏踊りが、やがて先祖を供養する盂蘭盆会(うらぼんえ)と結びついて、「盆踊り」になったと言われています。さらに時代が進んで、鎌倉時代中期になると、一遍上人(いっぺんしょうにん)が全国へ盆踊りを広めました。この時代になると仏教行事的な意味合いが薄れ、民俗芸能として庶民の間に定着して、娯楽的な意味合いが強くなりました。
更に江戸時代になると、盆踊りは各地域の人々の交流の場となり、男女の出会いの場にもなっていったということです。
旧暦7月15日の月夜
これは余分な話ですが、盆踊りが行われる夜は満月で、(旧暦7月15日)月明りだけで過ごすことができ、引力の影響で男女とも気持ちが高ぶり、出逢いに運命を感じやすかったのではないかという話しもあります。
そんな反面、その高ぶりは良い方向だけに働いたわけでもなく、警察の取り締まりが強化されることも多かったようです。
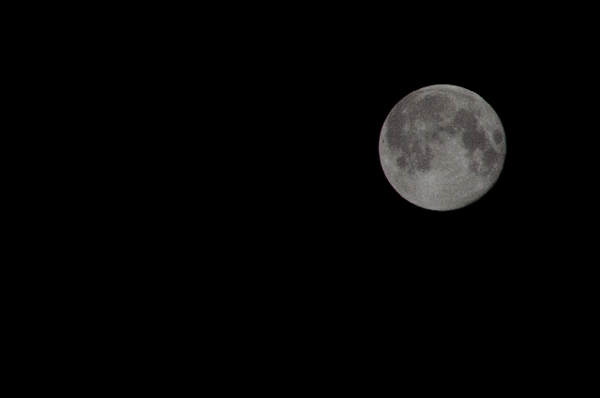
由来にお釈迦様「母を救いたい思い」
お釈迦様の十大弟子の一人である目連は、長い間の修行で神通力を得ました。そこで目連は、餓鬼道に落ちた母親を見つけて、ご飯を持って供養しようとしました。母親は喜んでご飯を食べようとしましたが、ご飯はたちまち火になって食べることができませんでした。
目連はお釈迦様に、どうしたら母親を救うことができるか尋ねました。
お釈迦様は、「お前の母は、一人子のお前に良い着物を着せたい、美味しいものを食べさせたいために罪を犯し餓鬼道に落ちたのだから、その罪は重い。これを救うには、十万の悟りを開いた僧侶の力を借りるしかない。
7月15日は、無罪相懺悔を修して悟りを深める日だから(聖日)、この日にあらゆる御馳走を供え、十万の僧侶による供養をすれば、僧侶たちの徳は大海のように限りないものなので、その功徳によって、おまえの母は救われるだろう」と言われました。
こうして、僧侶による供養が行われ、彼の母親は餓鬼道から救われました。目連は、母親が救われたことを喜んで、踊り狂ったと言います。そして、そこから盆踊りが始まったといいます。
子供のために罪を犯してしまった母。そんな母を救いたい想いが溢れた子供。今も昔も親子の愛は強いものですね。
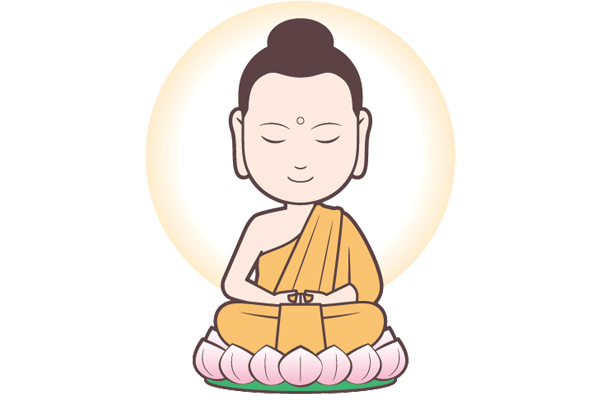
盆踊りの意味「精霊」か「悪霊」か
盆踊りが行われる意味には、複数の説があります。
成仏できた喜びの表現説
盆踊りの意味については、様々な説があります。お盆に戻ってきた精霊を慰め、餓鬼や無縁仏を送るための踊りだと言う説のほか、お盆の供養で成仏できた亡者が、喜ぶ姿を表現したものと言う説があります。
誘い込んだり追い出したり説
反対に、悪霊や亡者たちを踊りながら追い出すもの、お盆に戻って来た精霊たちを、踊りに誘い込んで送り出すものなどの説があります。
伝統文化的な意味合い
盂蘭盆会の仏教的意味合いが濃かった「盆踊り」は、やがて、伝統文化的な意味合いへと移行して、地域の人々の交流の場になっていったようですね。
「盆踊り」で思い出すのは、「炭鉱節(たんこうぶし)」です。年齢が若い人たちの間では、なじみがない人も多いかも知れませんが、この曲は「盆踊り」で必ず踊られる国民的な曲でした。
炭坑節の動画はこちらです。タイトルは知らなくても、曲を聞くとすぐにわかる人も多いのではないでしょうか?
日本三大盆踊り
日本三大盆踊りは、秋田県の西馬音内盆踊りと、岐阜県の郡上八幡盆踊り、そして徳島県の阿波踊りだとされています。
印象的な盆踊り
そのほか印象的な盆踊りには、高橋治氏の小説、「風の盆恋歌」で有名になった、越中おわら節にのせて踊る、おわら風の盆があります。
哀切に満ちたおわら節の旋律にのって、富山県八尾の町中を、無言で踊る踊り手たちの洗練された踊りが見事です。是非一度訪れてみてください。
盆踊りの起源と由来 まとめ
時代が変わっても、夏になるとお盆の行事をし、季節が秋へと変わる前に、人々は輪になって「盆踊り」を楽しみます。
行く夏を惜しむと同時に、お墓へ戻られたご先祖様を偲びながら踊る心の内には、日々の安寧と豊かな暮らしが続くようにとの願いが込められているのです。
今年の盆踊りは、ご先祖様へ思いをはせる夏にしてみるのもステキかも知れませんね。

この記事を読んだ人は、コチラの記事も読んでいます。
【初盆・新盆】の意味と準備・まつり方「お供えやお布施、精霊馬について」
今年も盆踊りが楽しみですね♪






